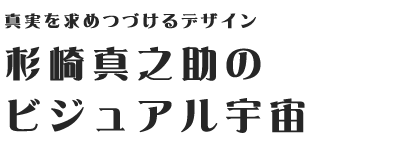
関西のグラフィックデザイン界のなかで、ひときわ強烈な存在感を放つグラフィックデザイナー、杉崎真之助氏。彼の生み出すビジュアル世界には、言葉を越えたメッセージとしてのデザインの可能性、あるいはデジタル技術が行き着く先のビジュアル・コミュニケーションの可能性が潜んでいる。今回はそのクリエイティブの本質を、あえて独断と偏見で読み解いてみた。
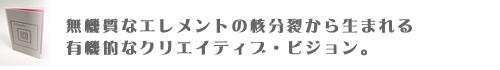
鮮烈なトーンでリズミカルに反復される無数の幾何学的フォルム。無機質であるはずの視覚的要素(ビジュアル・エレメント)は、核分裂のように猛烈なスピードで融合と摩擦を繰り返し、やがてエクスタシーの中で有機的なエネルギーを放ちはじめる。あたかも体温をもった生き物のように。まさにデジタル・デザインの宇宙のなかで生命体が誕生する瞬間、それが杉崎真之助のグラフィックデザインである。
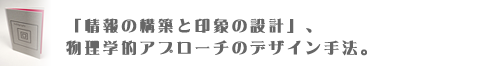
杉崎真之助は、デザインを「情報の構築と印象の設計」と定義づける。彼の手法は、ある種、物理学的あるいは量子力学的なアプローチといってもいい。
そもそもすべてを構成するものの本質はエネルギーであり、人間の思考もまたエネルギーである。現代物理学とくに量子力学的見解によれば、物質とエネルギーとの間には互換性がある。物質は高速エネルギーをもつ分子と衝突することで、物質性を破壊され、巨大なエネルギーへと変換される。
つまりこれと同じような現象が、杉崎真之助のグラフィックデザインの世界では起こっている。物質性をもった情報(ビジュアル・エレメント)にグリッドで一定の規則を与え、莫大な量へと増殖させ、複雑に構築し、衝突させることで、物質性を超え、ひとつの思考エネルギーをもったビジュアルを創出する。そこには過剰な情報を淘汰し、整理し、削ぎ落とし、発見していく杉崎真之助の思考プロセスが浮かびあがる。
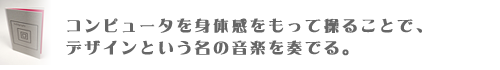
言うまでもなく、杉崎のグラフィックデザインに最も大きな影響をもたらしたのは、コンピュータとの出会いである。1980年代後半、杉崎はコンピュータと出会う。彼はコンピュータをデザインの手段として使うのではなく、コンピュータと一体化して表現することを選んだ。つまりコンピュータを自身の手や脳の延長のように、あるいは楽器のごとく、身体感をもって使いこなすことで、デザインという名の音楽を奏でようとしたのだ。杉崎のデザインの源流に、言葉よりむしろ音楽が感じるのはそのためだ。実際、彼自身、学生時代からの多感な時期をビジュアルよりも音楽に傾倒し、過ごした原体験がベースにある。
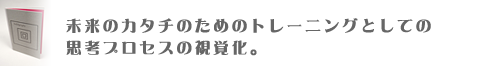
以来、脳内の心象風景にうつる思考プロセスを視覚化するために、杉崎のコンピュータとデザインとの格闘の日々は始まった。当初、杉崎は“未来のカタチのためのプロローグ”として、まるで基礎トレーニングのように実験的なアプローチを繰り返す。
1995年の個展「Invisible Shape(見えないカタチ)」では、人の裸体から人々の既成概念のなかにある輪郭をはずし、生命体としてのエネルギーだけを抽出して見せた。
2002年の個展「Elementism(エレメンチズム)」では、造形の視覚的要素の構築の可能性をあらゆる角度から検証し、表現した。そこには杉崎の造形に対するフェティシズムにも近い眼差しがある。
また2005年の個展「AONYMA(アノニマ)」では、さらに作家性や情緒を排除した匿名性を追求し、理性による新しいデザインを試み、よりクリアな表現を志向した。しかしながら逆説的にもそこに現れるのは、まぎれもなく杉崎真之助というクリエイターのもつ強烈な個性とビジョンである。
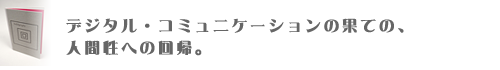
2007年、杉崎はともに大阪を拠点に活躍するアートディレクター高橋善丸とともに、ドイツのハンブルグ美術工芸博物館の招聘を受け、「真 善 美」杉崎真之助と高橋善丸のグラフィックデザイン展を開催する。この展覧会は、杉崎にとってこれまでのクリエイティブワークを総括する機会となり、よりデザインに対して客観的な眼差しをもつきっかけとなる。
さらに2008年末に同じく高橋とのコラボレーションで開催された「真and/or善 杉崎真之助と高橋善丸のグラフィックデザイン」では、「Solidgraphy(ソリッドグラフィ)」と題し、より自身を突き放し、自身とデザインとの関係性にも思考をめぐらせ、“間”という概念を取り入れた表現に至る。そこにかいま見えるのは、デジタル・コミュニケーションの果てに行き着いた人間性への回帰なのかもしれない。
2008年春の個展「デザインマイナスアート」では、シンプルなモノクロームの造形美を追求したシルクスクリーンの版画に挑戦。アート性を排することで、かえってアートとなり得る杉崎自身のデザインのもつ逆説的アイデンティティを浮き彫りにした。いずれにせよ彼のデザインには、日常のコミュニケーションデザインから実験的作品まで、一貫した思考、そしてアイデンティティが感じられる。
杉崎真之助の思考の旅は、これからも続くだろう。そして私たちがそこに見るのは、ひとりのクリエイターの思考を超え、ビジュアル・コミュニケーションの未来を示唆する新しいビジョンかもしれない。