 |
第四十四話 ほたえる
 |
|
前回が「いちびり」だったので、ついでながら「ほたえる」を--。
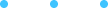
「いちびる」の意味のひとつに「ほたえる」も含まれている。ただ、いちびるの場合は、どちらかというと「おどける」といった道化系統の意味合いが強く、ほたえるの場合は、「ふざける・つけあがる」などの意味合いが強い。
現代語の辞書類を見ても、「ほたえる」とは、ふざけ騒ぐ、戯れるといった意味のほか、甘える、つけあがるなどの意味が指摘されている。
近松門左衛門は、この「ほたえる」という言葉がよほどに好きだったらしく、浄瑠璃作品の中に、盛んに使っている。
「お前は何処ぞ脇で遊んで下さんせと、いへどもほたえた顔付にて」(『心中天網島』上)、「こりゃん、ほたゆるなど、又引っがついて投げたがの」(『博多小女郎浪枕』)、「やい、かしましい、あたり隣もあるぞがし、よっぽどにほたえあがれ」(『女殺油地獄』中)、「若いなりしてびらしゃらと、あんまりほたえさっしゃるな」(『卯月の紅葉』上)--といった具合で、近松さんは、ほたえるマニアでもあったようだ。
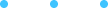
いま大阪で「ほたえる」を使うのシーンというと、子供たちをたしなめる時が多い。親や教師が、ふざけまわっている子供をしかる際に、「こら、ほたえな!」と一喝するようなケースである。大阪では若い母親なんかでも、ごくふつうに、「これ、あんたら、こんなとこで、ほたえなさんな」といったしかり方をしている。
大阪以外の人たちが耳にすると、ちょっと意味のわかりにく言葉かもしれないが、大阪人にとっては、わいわい、やいのやいのと騒いでいる状況を表現するのに、ニュアンス的にとてもよくわかる言葉のひとつだ。
本日のスキット
子供たちと母親の会話
| 長男 | 「このオヤツ、僕のもんな!」 |
|---|---|
| 次男 | 「あーん、お兄ちゃんずるい!」(オヤツを取り合いする兄弟) |
| 母親 | 「これ、あんたら、そんなことでほたえなさんな!」 |














