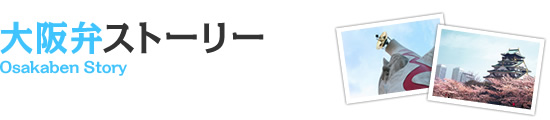文化を創る大阪弁

「江戸と『大坂』を比較してみる。江戸は将軍家のお膝元、旗本8万騎が守り固める警固都市。江戸の最盛期の人口は百万人で、そのうち侍は50万。2人に1人が侍だった。ところが大坂は、侍が少なかった。最盛期の人口は40万人で、侍はどんなに多く見積もっても四千を超えたことがない。圧倒的多数の市民が、市民自治を行き届かせて、商(あきな)いに明け暮れていた。だから、大坂は平和都市。明治になって『大阪』となったが、みんな平和主義者だから、あかんたれが多い。最大の経済都市は同時に最高の文化都市であったから、市民の文化性は大変洗練されていた」立命館大学教授・木津川計さんの談話からの要旨抜粋である。
明治以降の日本は、西洋から文化・文明を受け入れた。終戦を境に、日本文化の連続性もブチ切れた。そんな中にあって、唯一ブチ切れていない人間たちがいる。関西人である。彼らはどこに行っても、関西弁をしゃべる。たとえそれが海外でも、である。彼らは押さえつけられることを嫌う。少なくとも、他の地域からはそう見える。言葉も同じだ。いるものは受け入れ、いらんもんはほかす。しかし、関西弁のイントネーションだけはけっして捨てない。イントネーションは、彼らの背骨であり、考えるリズムであり、思考の足取りである。東京にしばらく行き、大阪に帰ってきた人がいまだに大阪弁をしゃべっていると、「あいつは、えらいやっちゃ」ということになる。大阪におけるその評価は高い。

関西人は、日本人の中でも、最もナチュラルに生き続けてきた人たちではないだろうか。それができたのも、経済力のおかげ。大阪府のGNPはメキシコやオーストラリアをしのぐと言われ、関西ではカナダ一国と比肩する。東京に行っても行かんでも、生活できる。文化が生まれるには、多少のゆとりと猥雑性が必要である。道頓堀の巨大なエビやカニが乱舞する町を、タコ焼きを頬張りながら歩けば、あなたも文化に突き当るかも。